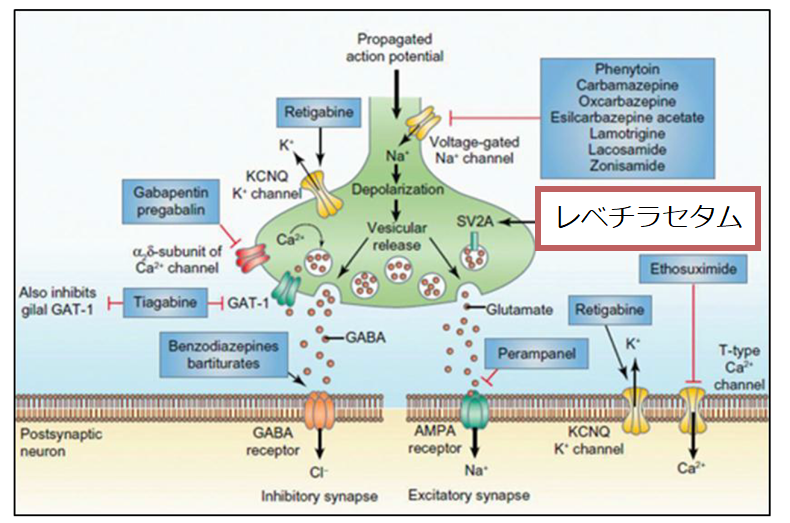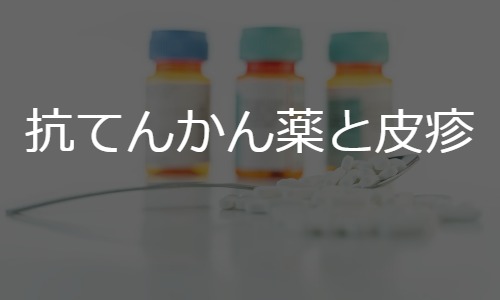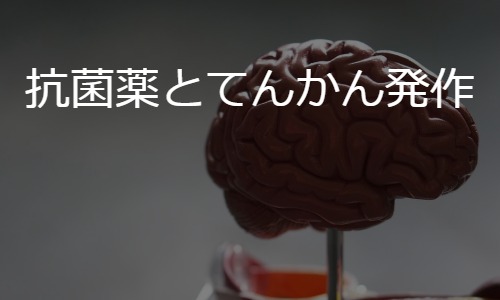NCSE: non-convulsive status epilepticus 非痙攣性てんかん重積
病態・分類 明らかな痙攣(convulsion)を呈さないてんかん重積である非痙攣性てんかん重責(NCSE)の存在は近年非常に有名になっており、救急領域でも知らない先生はおそらくいないと思います。認知は高まっていますが、個人的は注意点も多く感じます。 1:脳波検査を充分にせずにNCSEと判断する逆にあまりにもNCSEという言葉が有名になっているため「色々調べたけどよくわからなかったからきっとNCS […]