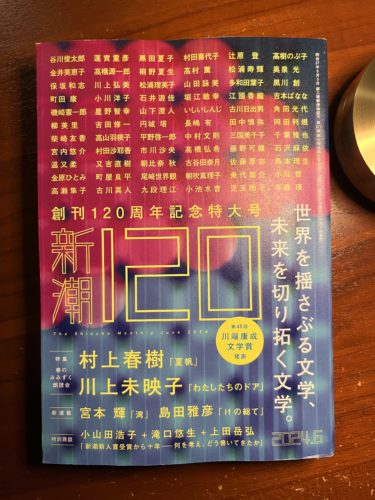厚生労働省が出している「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」改訂平成30年3月に関してです。表紙を除くと2ページという非常に短く、インターネットで誰でもアクセス可能(元のがこちら、解説編がこちら)です(確認までにこれは法律ではありません)。
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
具体的な内容は本文を読んでいただき、内容を私なりにまとめると以下になります。
・本人家族へ充分な説明と情報提供(誤解がないように)を行う
・医師1人で決めない、必ず多職種で話し合う場(多職種カンファレンス)を設ける
・本人の意思決定を基本とする (本人の意思は変化しうるため説明と確認を繰り返す)
・本人の意思が確認できない場合、代理意思決定者(親族に限定しない)による推定意思を尊重する
・代理意思決定者がいない、家族が決めることができないときは医療者に委ねられる
・いずれにせよ本人にとっての最善を考える
・治療ケアの開始・不開始・変更・中止を医学的妥当性を基に検討する
・緩和ケアを充分に行う
川崎協同病院事件
このガイドラインを考える上で重要な川崎協同病院事件に関して以下に少しまとめます。私自身法律の専門ではないため用語が少し間違えるところがあるかもしれません。この事件に関して私は恥ずかしながら現在勤務している病院のH先生から教えていただき、調べれば調べるほど医師であれば知っておくべき事件であると痛感しました。
経緯
1998年11月、元々気管支喘息で川崎協同病院に15年通院していた58歳男性の方が気管支喘息重積発作により心停止に至り、その後蘇生処置によりROSCするも低酸素脳症に至りました。自発呼吸は保たれており、人工呼吸器自体は離脱できましたが、気管チューブ(ここでは気管切開はなく挿管チューブ)は留置したまま管理され、その後ICUから一般床へ移動となりました。その後感染症合併などがあり、喀痰が気管チューブからどんどん噴き出している状態でした。家族からの抜管要請(ここは家族と医師の見解に相違があります)があり、家族が集まった後主治医により抜管されました。ここで複数の医療者による多職種カンファレンスはありません。
しかし、抜管後患者さんは呼吸が苦しい動作があり、苦痛緩和を目的として最初にセルシン、その後ミダゾラムが投与されました。それでも苦しそうな状況が持続していたため、最終的に筋弛緩薬ミオブロックが投与され(ここも医師と看護師に見解の相違があり、医師は自らミオブロックをICUから持ってきて生理食塩水に溶解して遅い速度でDIV、看護師は医師の指示下でミオブロックを3Aを静注)、その後に患者さんが死亡に至ったという事例です。
その直後は特に訴訟の話などはなかったのですが、3年後の2001年同病院の麻酔科医がこの件を取り上げて、主治医が刑事事件として起訴されました。そして最終的に殺人罪(懲役1年6か月年、執行猶予3年)の有罪判決に至りました。私は当時小学生でありこの事件について正直全く知らなかったのですが、マスコミも大きく取り上げ社会現象になったようです。
この際の主治医(外来、入院いずれも)である須田セツ子先生自身がこの事件に関して著書に記されています(これは2010年のもので、その後2024年版も出版されています)。私もこの本を読みました。また雑誌”Intensivist”の”End of life”特集のコラムでも主治医自らの記載があります。当事者の「医師からの視点」として色々と考えさせられるところがあります。
ポイントとなった2点
①自己決定の尊重
・家族からの要請は適切な医学情報が伝えられた上でなされたものではない
・患者の価値観や推定意思に関する検討が不十分
②治療義務の限界
・患者の予後推定をするための検査などが不十分であり、回復可能性に関して適切な判断が下せる状況ではない
管理人の一言
・私は医療倫理に関して今まで不勉強で、勉強するにつれて今までの自分の診療は本当に正しかったのだろうか?またどれだけ危ないことをしてきてしまっていたのか?という思いに駆られます。なので偉そうに響くところがあるかもしれませんが、私自身今勉強中の身です。ここ最近も色々な意思決定支援の現場があり、その中で感じたことを少し記載します。
言った、言っていないの「言葉」だけを追いかける水掛け論は不毛である 重要なのは「誤解なく伝わっているか?」
・患者さんが「痛いのは嫌だ」と言ったから、処置をしませんでした という言葉をよく聞きます。
・しかし、「一時的に痛みを伴ったとしても、それで〇〇が良くなる可能性が高いとすればどうですか?」と聞くと、「それならやってもいいかもしれない」となる場合があります。
・患者さんの「言葉」だけに着目して「あの時そういったじゃないか?」と問いただすのは「言った、言っていない」の水掛け論に行き着くことが多いです。
・しかし、ここで重要なのはやはり「適切に医学的状況を伝えた上で、患者家族に誤解がないか?」という点だと思います。経験上、そもそもここの段階で誤解があり医療者との間に乖離があることが非常に多いと思います。そしてここは私もかなり気を付けるようにしていますが、いまだに充分できている自信はありません。
・川崎協同病院事件でも「①自己決定の尊重」のところで「充分な情報提供があったか?」に関して指摘されており、前述のガイドライン上も指摘がある点であり極めて重要と思います。
予後を伝える、伝えないによって意思決定に相当大きな影響が生じる
・この充分な情報提供に関して「予後(生命予後・機能予後)」のことも含まれると思います。私たち医療者は頭の中で常にぼんやりと「この人の予後はこのくらいかな・・・」と思い描くことが多いですが、それは当たり前ですが言語化しないと患者家族には伝わりません。ここで医療者と患者家族の認識に齟齬が生じていることが多い印象があります。
・例えば患者家族は生命予後がまだ5年くらい生きることができると漠然と思っており、医療従事者側は生命予後が3か月くらいと想定している場合、その後の意思決定に大きな影響を及ぼします。これは生命予後だけではなく機能予後も同様です。
・もちろんここで医師側は医学的見地から予後を推定することが重要です。確かに腫瘍だと5年生存率などがありますが、正直症例ごとに検討しないといけません。またこれは難しいことです。なのでわからないことを前提に、多職種カンファレンスで複数の医師も参画して話し合うことを患者家族に予後を伝える前に(=事前に)行うべきだと思います。私自身集中治療部の医師とこの予後推定に関して話し合う機会があり、こうして話し合うことがとても助かります。
・予後を伝えることは医療者側、また患者家族側どちらにとっても心理的負担が大きいためつい躊躇されてしまうことがあります。ただ重要な意思決定支援においては必要な要素だなと感じます。
4分割表を使いバランスが歪になっていないか?要素が漏れていないか?を多職種カンファレンスで検討
・川崎協同病院事件では抜管前に多職種での検討はされておらず、主治医が1人で判断しています。
・前提として意思決定支援は患者家族やそれぞれの事情などがからみあい検討すべき点も多く、極めて複雑です。これを1人の頭の中だけで検討するのは純粋に限界があり(私の頭では無理です)、どうしても1人で判断するとバランス感覚を保つことが難しく、何かの要素が異常に肥大化してしまい他の要素を押しつぶしてしまう場合があります。
・ここでバランスを保ちながら必要な要素を検討する上で役立つのが多職種カンファレンスとジョンセンの4分割表と思います(下図H先生の資料を参考に作成)。私も2年前にこの方法を知り、実際に多職種カンファレンスで4分割表を用いると情報が整理されてとても良いです。経験上しばしば右下に位置する「周囲の状況」の要素が肥大しますが、これも表で整理すると可視化されて状況を把握しやすくなります。
・この4分割表を使い各要素を検討する、またそれをきちんと医師1人ではなく多職種で検討することが本当に重要と思います。
・このことに関して前述のガイドラインでも医師1人で判断するのではなく多職種で検討することの記載があります。
・またはここは主の目的ではないかもしれない、多職種カンファレンスは主治医を心理的に救います。経験上これは間違いないです。これら全てを主治医1人が背負って戦うのは心理的負担が大きすぎます。もちろん一番重要なのは最善の意思決定支援な訳ですが、主治医のバーンアウトを防ぐ意味合いにおいても個人的には重要な要素かと思います。

・まだまだ問題だらけではありますが、臨床をする上で避けて通れない重要なテーマであり、自分なりに考えていくことができればなと思っています。
参考文献
・終末期ディスカッション
・Intensivist 2012; vol4: No1: End of life. 「終末期医療の中止と刑事裁判例の歴史」