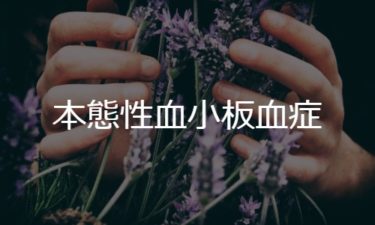医学の話題ではなく普通のブログ記事です。2024年6月15日(土)~16日(日)の2日間、早稲田大学の大隈講堂で「初夏の文芸フェスティバル」というイベントが開催されました。その企画(セッション)の1つとして村上春樹さんの短編小説を元にしたアニメ映画「めくらやなぎと眠る女」の特別上映会、またその後に映画監督(ピエール・フォルデスさん)と村上春樹さんのポストトークイベントが開催され、村上春樹ファンの友人2人と一緒に行ってきました。


映画「めくらやなぎと眠る女」
映画の公式サイトはこちら

映画のタイトルは「めくらやなぎと眠る女」ですが、実際には「めくらやなぎと眠る女」意外の複数の短編小説を有機的に組み合わせた内容になっています(「かえるくん、東京を救う」、「バースデイ・ガール」、「ねじまき鳥と火曜日の女たち」、「UFOが釧路に降りる」)。ほとんどが原作通りの内容なのですが(セリフもほとんど同じ)、ある作品と別の作品の人物がつながっている仕組みになっている点など、ところどころに映画オリジナルな要素も散りばめられています。例えば「UFOが釧路に降りる」の小村さんと「かえるくん、東京を救う」の片桐さんが同じ会社で働いているなど、それぞれの作品がつながりがあり面白いです。
観る前は正直「アニメ映画と村上春樹作品って相性いいのかな・・・?」と少し不安でしたが、いざ鑑賞してみると非常に面白く、「村上春樹さんの小説は意外とアニメ化が向いているのかもしれない」と感じました。また映像の色合いと音楽(音楽は監督自身が作曲されている点も驚き・・・)が作品の内省的な雰囲気と時折あるユーモラスな部分にとてもマッチしていました。アニメ作品というとどうしても少し子供向けな響きをイメージしがちですが、子供向けな要素は全くない作品でした。
またどうしてもリアリズムではない部分(非日常の混入部分)に実写の場合違和感を感じることが多いですが、アニメだとかなりスムーズかつ表現の幅が広がる印象があります。非リアリズムとリアリズムがくっきりと分かれれば問題ないのですが、こと村上春樹作品では日常と非日常が気づいたら入れ替わっている表裏一体な場面が多いので、いわゆる典型的なファンタジーとは異なり写実的に表現する際に難しそうだなと感じます。そういう意味で、ここ最近映画化された村上春樹作品の「バーニング(原作:納屋を焼く)」や「ドライブマイカー」はリアリズムの短編小説なので合っているのかもしれません。
また今回映画を観て驚いたことは、自分が原作を読んだときにイメージしていた情景と映画での映像がかなり似通っていた点です。それも日本について詳しくない海外の監督が作った作品にもかかわらず、このように日本の映像風景が似通ったものになるところは、何かしらの根源的かつ世界的な共通点のようなものが村上春樹作品には流れているのかもしれません(これは海外でも村上春樹作品が読まれていることとも関係しているかと思いますが)。
個人的に楽しかったシーンは「かえるくん、東京を救う」のかえるくんと片桐さんが初めて対面して会話するシーン、「バースデイガール」でイタリアンレストランのサーブ係の女の子が料理を支配人に届けて願い事の話をするところです。これは実際に映像でみるとより世界観が広がる感じがありました。
今回音声は英語で字幕が日本語でしたが、2024年7月に日本語吹き替え版が公開されます。とても面白かったので、改めて日本語吹き替え版でもまた楽しみたいなと思います。
参考:今回映画に収録されている作品の紹介
「めくらやなぎと眠る女」は短編集「螢・納屋を焼く・その他の短編」に収録されています。
短編集の「神の子どもたちはみな踊る」には「かえるくん、東京を救う」、「UFOが釧路に降りる」が収録されています。いずれも「地震」がテーマになっている作品です。特に「かえるくん、東京を救う」はかなりファンが多い短編作品と思います。私は「UFOが釧路に降りる」でシマオさんが主人公の小村に最後に放つ言葉が、時間軸をぐっとゆがめゾッとするような恐怖感があって好きな作品です。
「バースデイ・ガール」は赤を基調としたイラストが背景にあり視覚的にも楽しむことができる私自身とても好きな素敵な作品です(短編集に収録されておらず、文庫本もないです)。この作品を読むと誰もが「願い」に関してじっくりと考える機会に触れることができます。中学校の国語の教科書に取り上げられていると今回知り非常に驚きました(今の中学生がこうした素晴らしい文章に触れることができるのは羨ましい限りです)。
ポストトーク
司会は権慧さんが務められ、翻訳家の柴田元幸先生(村上春樹さんと翻訳関連で親交が深い)が会話をすすめる中心となって村上春樹さんと監督のピエール・フォルデスさんのトークが進みます。ピエール・フォルデスさんは英語で、柴田先生がときおり通訳をはさみながら(別に同時通訳もあります)、村上春樹さんは日本語で回答していました。細かい内容は失念してしましましたが、以下にざっくりと話の趣旨まとめます。
村上春樹さんによる映画の感想
・アニメ映画を普段観ることはないが、今回はとても楽しむことができた。
・今回の短編作品はどれも年十年も前に書いた作品なので内容をあまり覚えておらず、次どうなるのだろうと楽しみながら観ることができた(会場が笑いにつつまれる)。
→ちなみに前回の川上未映子さんとの朗読会でも村上春樹さんは自分の過去の作品は読み返していないから覚えていないという話をされておられます
村上春樹作品の映画化に関してのコメント
・長編の場合は映画の尺にあわせるために内容を削っていかないといけないが、短編の場合は映画化するために映画を作る人が作品内容を独自に膨らませることが面白い点と思う。このため基本的には短編が映画化には向いているのかもしれない。
・ここ最近の作品(具体的にはバーニングとドライブマイカーを挙げられ)は双方(村上春樹さん側も映画監督側も)の思いが繋がり上手くいってきている感じがある。
村上春樹さんが今後映画化して欲しい自身の作品に関して
・「アンダーグラウンド」と即答。
・日本人の多重的なボイスを表現する上で映画が適しているのではないかと考える。
→「アンダーグラウンド」への村上さん自身の熱い想いを感じました。この作品は地下鉄サリン事件での被害者の方へのインタビューを村上春樹さん自身が徹底的かつ長期間にわたる綿密な取材を通してまとめられたノンフィクションの作品で、村上春樹さんの作品の中では極めて異質です。私は「アンダーグラウンド」の最後、「目じるしのない悪夢」での文章に心を打たれてしばしば読み返しています(自分への戒めも込めて)。私たち日本人にとって極めて重要な文章だと思うのでここに引用させていただきます。
そのようにして人々は多かれ少なかれ、「正義」「正気」「健常」という大きな乗合馬車に乗り込んだ。それらは決してむずかしいことではなかった。そこでは相対性と絶対性が限りなく近接していたからだ。
・・・中略・・・
「正気」の「こちら側」の私たちは、大きな乗合馬車に揺られていったいどのような場所にたどり着いたのだろう?私たちはあの衝撃的な事件からどのようなことを学びとり、どのような教訓を得たのだろう?
ひとつだけたしかなことがある。ちょっと不思議な「居心地の悪さ、後味の悪さ」があとに残ったということだ。私たちは首をひねる。それはいったいどこからやってきたのだろう、と。そして私たちの多くはその「居心地の悪さ、後味の悪さ」を忘れるために、あの事件そのものを過去という長持ちの中にしまい込みにかかっているように見える。そして出来事そのものの意味を「裁判」という固定されたシステムの中でうまく文言化して、制度レベルで処理してしまおうとしているように見える。
・・・中略・・・
もしそうだとすれば、いったいどこでボタンの掛け違えが始まったのだろう?
私たちがこの不幸な事件から真に何かを学びとろうとするなら、そこで起こったことをもう一度別の角度から、別のやり方で、しっかりと洗いなおさなくてはいけない時期にきているのではないだろうか。「オウムは悪だ」というのはた易いだろう。また「悪と正気は別だ」というのも論理自体としてはた易いだろう。しかしどれだけそれらの論が正面からぶつかりあったとしても、それによって<乗合馬車的コンセンサス>の呪縛を解くのはおそらくむずかしいのではないか。
というのは、それらは既にあらゆる場面で、あらゆる言い方で、利用し尽くされた言葉だからだ。言い換えれば既に制度的になってしまった、手垢にまみれた言葉だからだ。このような制度の枠内にある言葉を使って、制度の枠内にある状況や、固定された情緒を揺さぶり崩していくことは不可能とまではいわずとも、相当な困難を伴う作業であるように私には思えるのだ。
とすれば、私たちが今必要としているのは、おそらく新しい方向からやってきた言葉であり、それらの言葉で語られるまったく新しい物語(物語を浄化するための別の物語)なのだ-ということになるかもしれない。
・・・中略・・・・
前にも書いたように、この事件を報道するにあたってのマスメディアの基本姿勢は、<被害者=無垢なるもの=正義>という「こちら側」と、<加害者=汚されたもの=悪>という「あちら側」を対立させることだった。そして「こちら側」のポジションを前提条件として固定させ、それをいわば梃子の支点として使い、「あちら側」の行為と論理の歪みを徹底的に細分化し分析していくことだった。
このような相互流通性を欠いたモーメントの行き着く先は、往々にして、煮詰められパターン化された論理であり、淀みがもたらす無感覚である。
事件発生後しばらく経過したころから、私は漠然とではあるがこうした考えを抱くようになっていた。この地下鉄サリン事件の実相を理解するためには、事件を引き起こした「あちら側」の論理とシステムを徹底的に追及し分析するだけでは足りないのではないか。もちろんそれは大事で有益なことだが、それと同じ作業を、同時に「こちら側」の論理とシステムに対しても並行して行っていくことが必要なのではなるまいか、と。「あちら側」が突き出してきた謎を解明するための鍵は(あるいは鍵の一部は)、ひょっとして「こちら側」のエリアの地面の下に隠されているのではあるまいか?
つまりオウム真理教という「ものごと」を純粋な他人事として、理解しがたい奇形なものとして対岸から双眼鏡で眺めるだけでは、私たちはどこにも行けないんじゃないかということだ。たとえそう考えることがいささかの不快さを伴うとしても、自分というシステム内に、あるいは自分を含むシステム内に、ある程度含まれているかもしれないものとして、その「ものごと」を検証していくことが大事なのではあるまいか。私たちの「こちら側」のエリアに埋められているその鍵を見つけないことには、すべては限りなく「対岸」化し、そこにあるはずの意味は肉眼では見えないところまでミクロ化していくのではあるまいか?
アンダーグラウンド 村上春樹
感動:川上未映子さんと握手させていただく
映画が始まる前に自席から5列くらい前の関係者席に川上未映子さんがいらっしゃることに気付きました。川上未映子さんは村上春樹さんと親交が深く、対談本を出されていたり、先日は一緒に朗読会(こちら)を開催されていらっしゃります。
素敵な服をまとい凛とされたお姿で、並々ならぬオーラを放っていらっしゃったのですぐに「あっ、川上未映子さんがいる!」と気が付きました。一緒に来ていた友人に「ねえねえ、川上未映子さんがいる!!」と興奮しながら話しながら、さすがに関係者席に行って声をかけるのは図々しすぎるため「うーん・・・なんとか、少しでもお話できればなー・・・」と思っていました。
そもそも川上未映子さんがファンから声をかけられることをあまり快く思っていらっしゃらない場合ただの失礼になってしまうので、過去の川上未映子さんのエッセイで「ファンから声をかけられることへのポジティブまたはネガティブな言及があっただろうか?」と記憶の引き出しを一生懸命に探りましたが、一切思い出せません(ちなみに村上春樹さんは自身のエッセイでしばしばファンに声をかけられて困った経験を記載されています)。うーん勇気をもってお声がけしてよいものかどうか・・・。
終演後、座席から立ち上がりぞろぞろと出口に歩く廊下で、川上未映子さんがすぐ近くにいらっしゃりました。迷惑かなと躊躇いながらもつい勢いで「川上未映子さん・・・、黄色い家とっても好きです。すみません握手お願いしてもよろしいでしょうか?」と声をかけてしまいました。あまりの緊張と川上未映子さんの放つオーラに圧倒され、なかなかお顔をじっと見て話すことができず、声もごにょごにょしてしまいましたが・・・川上未映子さんは素敵な笑顔で握手も対応していただき、「先日の朗読会も参加させていただきました」と私がごにょごにょ話すと、「これからも応援お願いします」と明るい笑顔で返事をしてくださりました。また出口への通路で声をかけてしまったこともあり、出口まで同じ方向へ歩く時間で少しだけ映画の感想などをお話することが出来ました。本当に幸せな時間でした。川上未映子さんの本とサインペンを持ち歩いていなかったことが悔やまれます(笑)。
「何事も勢いと積極性が大事!」という図々しい教訓を得て、大隈講堂を後に帰路につきました。